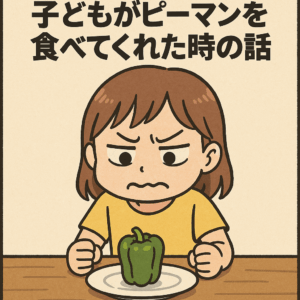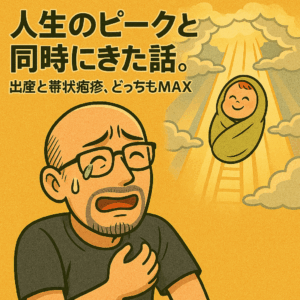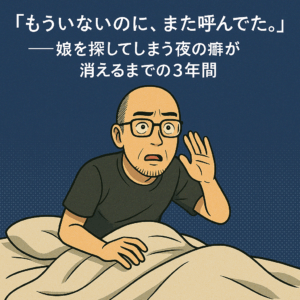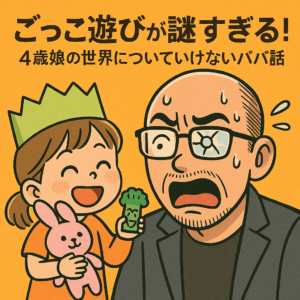はじめに:ママだらけの公園で、私だけ場違いだった
あれは、娘が幼稚園の年長だった頃。私は平日昼間も娘と過ごすことが多く、毎日のように近所の公園に通っていました。午前中の静かな時間帯か、帰園後の夕方。娘は砂場が大好きで、私はベンチで見守りながら、その時間を大切にしていました。
でも、公園に行くたびに感じていたのが、「この場所はママの世界なんだな」という空気感でした。ブランコの横、滑り台の前、日陰になっているベンチには、顔見知りのママたちが集まり、おしゃべりに花を咲かせている。そこに、私――つまり主夫の男がひとり混じると、空気が少しだけ張り詰めるような気がしてならなかったんです。
誰も悪意があるわけじゃない。みんな自然体で、楽しく過ごしているだけ。それなのに、私はそこに「いてはいけないような感覚」に、いつも包まれていました。
主夫として育児をしていた頃、娘との時間は何よりも尊く、愛おしいものでした。一方で、こうした“社会の中の孤立”を感じる瞬間があるのも、正直なところです。
この記事では、そんな私が公園で感じた居心地の悪さ、孤立感、そしてそれをどう受け止め、乗り越えてきたかを振り返ります。同じような立場にいるパパたち、かつての私のように「居場所がない」と感じている人の力になれたら嬉しいです。
なぜパパは浮いてしまうのか?
娘と公園に通っていた当時、何度も感じたのが、「ここにいる私は、なんだか異物なんじゃないか」という感覚でした。誰にも責められていないのに、勝手に肩身が狭くなる。それにはいくつかの理由があったと思います。
1. ママの比率が圧倒的に高い
平日の公園は、ほとんどがママと子ども。私がいると、どうしても目立つんです。服装も、雰囲気も、話している内容も、まるで違う。あの頃はまだ、主夫という存在が今よりも珍しく、公園での男性の姿は浮きやすいものでした。
2. ママたちの輪に入る難しさ
顔見知りのママ同士が集まって話している輪の中に、突然男性が加わるのは難しい。たとえ共通の話題――たとえば幼稚園のことや行事のことがあっても、会話に入るタイミングがわからない。結局、私はいつも距離を保っていました。
3. 「自分だけ浮いている」感覚が膨らむ
ママたちの笑い声や、自然なやりとりを横目に見ながら、私は「ここにいるべきなのか?」と考えることがありました。誰も何も言わないのに、自意識だけが勝手に膨らんでしまう。たぶん、それが一番の原因だったのかもしれません。
でも今振り返ると、それはすべて「慣れていないだけ」だったんだと思います。
育児という日常の中で、“異質”な存在としてのパパがそこにいるだけで、違和感を覚えてしまうのは仕方のないこと。でも、その違和感は、ちゃんと工夫すればやわらげることができました。
ママコミュニティはどうしてあんなに強固なのか
公園に行くたびに、ママたちのつながりの強さを感じていました。誰かが来れば自然に会話が始まり、次から次へと話題が尽きない。まるで“公園支部の井戸端会議”のような雰囲気。そこには安心感と一体感がありました。
当時の私は、その輪の外にぽつんと座って娘を見守っていることがほとんどで、「なぜこんなにも結束しているんだろう?」と、少し不思議に思っていました。
1. 園の送迎が生む“日常の顔なじみ”
ママ同士は、幼稚園や保育園の送迎で毎日のように顔を合わせているんですよね。運動会、参観日、お迎え時のちょっとした立ち話――その積み重ねが自然と関係性を育てていく。私は送り迎えの回数も少なかったので、そこからすでにスタートラインが違っていたのかもしれません。
2. 情報交換という名の連帯感
ママたちの会話をよく聞いてみると、子どもの体調、担任の先生、園のおたより、予防接種の情報など、日常の“共有”が中心でした。誰かの困りごとに共感したり、知っている範囲でアドバイスしたりするやり取りの中に、連帯感が生まれているように感じました。
3. 非言語の「空気」で回るグループ
私は会話に入っていなくても、輪の中の“空気感”はなんとなく伝わってくるんです。アイコンタクトやリアクションのタイミング、会話のリズム――そのすべてが、ある種の“文化”になっているようでした。
そこに突然現れた私が、何も知らずに会話に入ろうとするのは、やっぱり無理がある。それに気づいてからは、「入りたい」ではなく「離れていてもいい」という意識に切り替えました。
彼女たちの世界には敬意を持って距離を置き、自分なりの居場所をつくること。それが、私にとって一番心地よいやり方でした。
会話ゼロでもOK。私が意識していた3つの立ち位置
私は公園で、誰とも話さずに過ごす日がほとんどでした。それでも、「浮かないようにする」ために、あるいは「違和感のある存在にならない」ために、意識していたことが3つあります。
1. 挨拶だけは、毎回きちんとする
「こんにちは」「お疲れさまです」――たったこれだけの言葉が、公園という空間における“存在の承認”のように感じていました。返事があってもなくても、私は毎回挨拶をしていました。それは、周囲との関係を深めるためではなく、その場にいる権利を自然に表現するためでした。
2. 娘と一緒にちゃんと遊ぶ
私はベンチでスマホをいじるのではなく、娘と遊ぶことに集中していました。砂場で一緒に山を作ったり、ブランコを押したり。周囲の目を気にするよりも、目の前の娘の表情を見ることのほうがよっぽど大事だったからです。
結果的に、「あのパパ、ちゃんとしてるね」と思ってもらえていたのかもしれません。言葉を交わさなくても、“子どもに向き合っている大人”という印象を与えることはできると実感しました。
3. “座る場所”を工夫する
これは地味ですが意外と大事で、ベンチのど真ん中や、ママたちが密集しているところは避け、ちょっと離れた位置に座るようにしていました。かといって完全に孤立するのではなく、適度な距離感を保つ場所に。これだけで空気がぐっと柔らかくなったように思います。
話さなくてもいい。ただ、“いて当たり前の存在”になることが、私の中での目標でした。
娘がくれた“接点”という名の魔法
公園にいる間、私が周囲のママたちと接点を持てた数少ないタイミングは、娘を通じて会話が生まれたときでした。
ある日、娘が同じ年頃の女の子とすぐに打ち解け、砂場で一緒に遊び始めたことがありました。その子のママが近くにいて、私に「うちの子、すぐ仲良くなっちゃってすみません」と声をかけてくれたんです。
「いえいえ、こちらこそ。一緒に遊んでもらって助かります」
そんな、たったひと言のやり取りが、公園での私にとってはとても貴重で、温かい経験でした。
子どもが生む“自然な入口”
自分から誰かに話しかけるのは難しくても、子ども同士が関わりを持つことで、大人同士にもごく自然な接点が生まれる。
これは、私にとって公園での「孤立感」を少し和らげてくれる、大きなヒントでした。
家に帰ってからの“会話のヒント”を覚えておく
「今日は〇〇ちゃんと一緒に滑り台した!」と娘が楽しそうに話してくれる日がありました。
そんなときは、次にその子に会ったときに「今日も一緒に遊べるといいね」など、軽く話題を振るようにしていました。すると相手のママも「あ、また会えましたね」と笑顔で応じてくれることが多くなったんです。
接点をくれたのは、いつも娘でした。
私はそれを、“魔法”のように感じていました。
「輪に入れない=失敗」じゃないと気づいた日
最初の頃の私は、公園にいるたび「会話に入れない=うまくやれていない」と思っていました。誰とも話さずに1時間、2時間過ぎると、「今日もまた浮いてたな」とため息をついたこともあります。
でも、ある日ふと、娘が笑顔で「今日は楽しかったね」と言ってくれたとき、私はハッとしたんです。
「あれ、私って本当に“失敗”してたのかな?」と。
娘が満足していれば、それが100点
その日の娘は、ブランコで思い切り風を感じて、砂場でごちそうを作って、滑り台で「見てて!」と何度も声をかけてくれた。私は、ちゃんと見て、ちゃんと応えて、ちゃんと笑っていました。
ママたちの輪に入ることはできなかったけれど、娘との関係性の中では、ちゃんと自分の役割を果たしていた。
「輪の中」じゃなくても“場の一員”になれる
その日から私は、“馴染めない自分”を責めることをやめました。公園で子どもと過ごしているということ自体が、すでにその空間の一員なのだと、自分に言い聞かせました。
それからは、話しかけられなくても落ち込まない。誰かと笑い合えなくても気にしない。
輪の外にいることは、失敗じゃない。公園は、誰もが自由に過ごしていい場所なんです。
それでも孤独なとき、私が頼った場所たち
いくら気持ちを切り替えても、公園でひとり、誰とも言葉を交わさない時間が続くと、やっぱり孤独が顔を出すこともありました。
そんなとき、私は「自分なりに安心できる場所」をいくつか持っておくことで、気持ちのバランスを取っていました。
1. 児童館という“居場所”
雨の日や寒い季節、娘とよく通っていたのが近所の児童館でした。ここではスタッフの方が気さくに声をかけてくれたり、たまに他のパパと話す機会もありました。
公園よりも“公的な空間”だからか、孤立感を抱えずにいられる場所だったように思います。娘も絵本やおもちゃに夢中になれて、私自身も安心して過ごせる空間でした。
2. オンラインでのつながり
誰かに話したい気持ちが強いときは、X(旧Twitter)で「#主夫」や「#育児パパ」といったハッシュタグを検索して、同じような立場の人のつぶやきを読んでいました。
「わかる」「それ自分もやった」って思える投稿があるだけで、見えない仲間がどこかにいるような気がして、ずいぶん救われました。
3. 幼稚園の送り迎えでの“挨拶コミュニケーション”
たまに娘の送り迎えをする機会があるときは、他の保護者や先生と挨拶を交わすだけでも、孤独感がやわらぎました。ほんのひと言でいいんです。「今日は寒いですね」「〇〇ちゃん、いつも元気ですね」――そんな些細な言葉のやり取りが、私にとっては貴重な“社会との接点”でした。
孤独に強いフリをしなくてもいい。
主夫だったあの頃、週5で通った公園で見つけた答え
娘が年中から年長にかけての2年間、私はほぼ毎日のように公園へ通いました。天気が良ければ外へ、雨が降れば児童館へ。それが“日課”になっていた時期です。
最初の頃は、「浮いてないかな」「場違いじゃないかな」と周囲の空気を気にしてばかりでした。でも、季節がひと回りする頃には、気持ちが大きく変わっていました。
「誰とも話さない時間」にも意味があった
誰とも話さなくても、娘と一緒に過ごしている時間は、かけがえのないものでした。
砂場でケーキを作って、「パパも食べて」と差し出してくれるその手。ブランコで高くこいで、「見ててね!」と笑う顔。それを一つひとつ、ちゃんと見届けられる自分でいられること。
それだけで、私は十分だったのかもしれません。
“存在すること”自体が意味になる
毎日通ううちに、他のママたちや子どもたちとも自然と顔を覚え合い、声はかけなくても目が合えばうなずく程度の関係になっていました。
輪の中には入っていないけど、誰からも排除されていない。
そう思えるようになるまでには時間がかかりましたが、私はそれを「受け入れられた証」だと感じていました。
無理をしないことで、子どもも自然に笑う
何よりも嬉しかったのは、娘が毎日楽しそうだったこと。どの公園にも「自分の場所」ができていて、あいさつする友だちも増えていきました。
私が無理をしないことで、娘も安心して過ごせていたのだと思います。
主夫だったあの頃、公園で学んだのは、「育児は戦いじゃなく、対話」だということでした。
誰かと張り合う必要も、目立とうとする必要もない。目の前の子どもと、静かに、丁寧に向き合うこと。
それが、私なりに見つけた“公園という世界”との付き合い方でした。
まとめ:娘が笑っていた、それで十分だった
主夫として娘と過ごした日々の中で、公園という場所は私にとって“ちょっとした試練の場”でもありました。
周囲のママたちに囲まれて、たった一人のパパがベンチに座っている構図。最初は気まずさと疎外感ばかり感じていました。
でも――
娘が笑っていた。何度も「パパ、見て!」と呼んでくれた。
その声に応え、目を合わせて、同じ時間を過ごしていた。
それだけで、私はそこに“いてよかった”のだと、今なら胸を張って言えます。
会話がなくてもいい。輪に入れなくても構わない。親としてそこにいること、その場で子どもを見守っていること。それが、何よりの役割でした。
今、私は娘と一緒に暮らしてはいません。だけど、あの公園で過ごした時間は、確かに“父としての私”を育ててくれました。
だから、もしも今、公園でひとり浮いているように感じているパパがいたら、私は伝えたい。
大丈夫。その時間には、ちゃんと意味がある。
そして、子どもが笑ってくれていたなら、それがもう正解なんです。