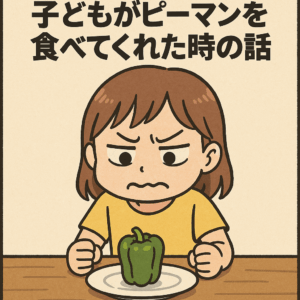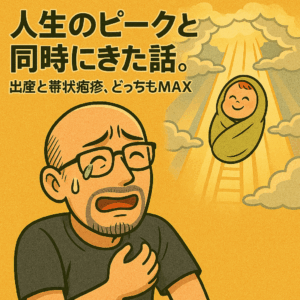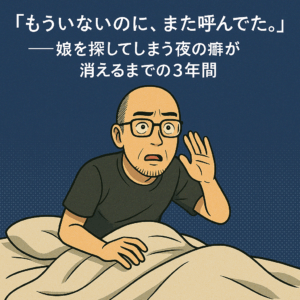“ごっこ遊び”の記憶は、週末の再会で蘇る
「パパ、きょうは“プリンセスやさいレストラン”ね。パパはキャベツの国のしんじゅう王子!」
……キャベツの国?しんじゅう?野菜なのか貝なのか、どっち?
私は今、週に一度だけ、娘と会っている。親権はないけれど、週末になると30分でも1時間でも、こうして会える時間がある。
そのたびに思い出すのが、かつて一緒に暮らしていた頃の「ごっこ遊び」の数々だ。
あの頃は、毎日のように意味不明な設定で遊びに誘われていた。言葉のルールも展開も彼女の中で完結していて、私はつねに“配役ミス”を怒られてばかりだった。
当時は正直、ヘトヘトだった。でも今となっては、あの混沌とした時間が、愛しくてしかたない。
この記事は、そんな「ごっこ遊び」と私の戸惑いと成長(?)を綴る回想録だ。
ごっこ遊び、第一難関「役が謎すぎる」
一緒に暮らしていた頃、夕食後のルーティンのように始まるのが「ごっこ遊び」だった。
私はソファに倒れ込みたい疲労感と格闘しながらも、「じゃあ今日は何する?」と尋ねる。
娘は目をキラキラさせて言う。「うんとねー、パパは“さかなくんのおにいちゃん”で、私は“パン屋のきょうりゅうのママ”!」
さ、さかなくんのおにいちゃん??パン屋で恐竜でママって何?
この時点で、私の頭は思考停止。しかも演技開始と同時に、彼女の頭の中には細かい設定がすでに完成していて、少しでもズレた発言をすると、
「ちがう!そうじゃないでしょ!」
と即座に怒られる。
「え、でもパパは魚売る人じゃなかった?」「ちがうよ!おにいちゃんは魚を持ってくるだけで売っちゃダメなの!」
……え、それはもう“売ってる”のでは?と突っ込みたくなるのをこらえながら、私の頭の中には「ごっこ遊びマニュアル」が欲しい…という悲鳴が響いていた。
でも、そんなふうに困っている私の顔を見るのもまた、彼女にとっては面白かったのかもしれない。
娘のルールは絶対!?「即興台詞劇」の世界
ごっこ遊びを一言で表すなら、“即興台詞劇(アドリブ芝居)”だ。
ただし、その脚本は私ではなく娘がすべて握っている。
ある日は「森のケーキやさんごっこ」。私は「空から来たおきゃくさん」として登場させられた。設定の段階で「お空の国のルールでしゃべって」と言われる。
「こんにちは」じゃなくて「ピヨンチュー」と言うよう指示され、「いただきます」は「ケキリシャマ」になるらしい。
もちろん私は毎回忘れる。何度も普通に「こんにちは〜」と言って怒られる。
「パパ、それちがうってば!もういっかい、ピヨンチューって言って!」
正直、笑ってしまう。
だって、「ピヨンチュー」って何?どこから来たんだその単語?
だけど娘にとっては大真面目だ。彼女の中では「空の国」はきちんと存在していて、その国の文化や言葉、挨拶や食べ物があって、私はその世界観を守らなければならない。
私はうっかり“セリフ”を間違えるたびにNGを出され、「本番」までリテイクが繰り返される。
気がつけば、私は彼女の世界の中で何度も「演じ直し」を命じられる立場になっていた。
「お店屋さん」でもガチで怒られるパパ
ある日、娘が「今日はおみせやさんごっこね!」と言って、ダンボールと紙皿を並べはじめた。
「いらっしゃいませ〜」という声に合わせて、私はお客さん役として登場。
「こんにちは、ハンバーグください」と言った瞬間、娘の表情が固まった。
「……ちがうよパパ、ここは“ケーキ屋さん”だもん」
しまった。紙皿の上の茶色い物体が、ハンバーグに見えた。だって色と形がどう見ても……。
「これはチョコケーキ。こっちはイチゴの山。で、これは“ピーマンまん”」
ピーマンまんってなに。
「ごめんごめん、じゃあこの“ピーマンまん”ください」
すると娘は、突然「店、しまいましたー!」とダンボールをバタンと倒して終了。
怒ってる……完全に怒ってる。
「パパはちゃんと見てないでしょ。いつもふざけるもん」
たしかにふざけた。というか、私からしたらそれは“ふざけてる”つもりじゃなく、“なにが正解かわからない”状態なのだが、彼女の目には明らかに“適当にしてる”ように映っていた。
この瞬間、私は理解した。
ごっこ遊びとは、「本気のやりとり」なのだ。
私が「適当」に見えてしまえば、彼女はそれを感じ取ってがっかりする。たとえそれが紙とガムテープでできた小さな世界でも、彼女にとっては現実なのだ。
逃げたいけど逃げられない、なぜなら…
正直、ごっこ遊びはしんどかった。
仕事でクタクタな日も、夕食後の洗い物が山積みの日も、「ごっこやろう〜!」の一言から始まる即興演劇に巻き込まれる。
「ちょっとだけ休ませて」が通用しないのが4歳児。リモコンを手に取ろうものなら「テレビはダメ!王様がくるのに!」と全力で止められる。
台本もない。終わりもない。こちらが疲れてグダグダになると、「もういい、パパへたくそ」とまで言われる。
……ちょっと泣きたくなる。
「逃げたい」と思ったこともある。でも逃げなかった。いや、逃げられなかった。
なぜなら、彼女がそんなふうに全力で向かってきてくれる時間が、永遠じゃないと、うっすら気づいていたからだ。
彼女がこうして「パパ、遊ぼう」って言ってくれる日は、いつまで続くだろう。
きっとあと数年もすれば、「パパと遊ぶのダサい」と言われる日が来る。
そう思うと、わけのわからない役でも、謎のセリフでも、「演じてみるか」と思えてしまうのだった。
娘の一言に、グサッとやられた日
ごっこ遊びの最中、私はついスマホを手に取ってしまった。
「ちょっとだけ仕事のメール見るから、待っててね」
娘は黙ってうなずいた。ふだんなら「やだ!今やってるのに!」と怒るのに、その日は静かだった。
数分後、スマホを置いて「ごめんね、続きやろうか」と声をかけると、娘は小さな声でこう言った。
「パパ、ほんとはあそびたくないんでしょ」
胸にズシンときた。
そんなつもりはなかった。けれど、彼女にとっては“そう見えた”のだ。
私は全力で否定し、「パパはあそびたいよ。でも、ちょっとだけおしごとも大事なんだ」と説明した。
でもその言い訳がどれだけ響いたかはわからない。
その日は結局、ごっこ遊びは再開されなかった。
私は洗い物をしながら、静かになったリビングを見て思った。
彼女にとってのごっこ遊びは、ただの遊びじゃなかった。私とつながるための手段だったのだ。
そして私は、そのチャンスを自分から手放してしまった。
ごっこ遊びの意味に気づいたとき
あの日以来、私はごっこ遊びに対する意識を変えた。
「変な役ばかり」「セリフが謎」「終わりがない」――たしかにそうだ。でもそれ以上に、ごっこ遊びは、娘が私に話しかけるための“言葉”だった。
「ママがいない」「保育園でイヤなことがあった」「今日はさみしい」――4歳児はそんな気持ちを、うまく言葉にできない。
でも、ドラゴンのお姫さまになったり、空飛ぶラーメン屋になったりしながら、私とのつながりを確認していたのだと思う。
そして私も、全力で付き合ううちに、いつの間にか笑っていた。演じることに夢中になり、「もっとこうしたら面白いかな?」なんて考えるようになっていた。
「遊び」は、いつしか「対話」に変わっていた。
言葉では伝えられない気持ちが、紙コップと空き箱でつくった“物語”を通して、確かに私に届いていた。
今も続く“週末劇場”のありがたさ
今、私は彼女と一緒には暮らしていない。生活は別々だ。
でも、週に一度、ほんのひとときだけでも会える。
そしてその時間は、やっぱり「ごっこ遊び」から始まる。
リュックからぬいぐるみを取り出して「この子がきょうびょうきなの」と始まる遊び。
私が動物病院の先生をやったり、アイス屋さんのバイトをやったり。配役はだいたい“脇役”だ。
だけど私は今、それがどれだけ幸せなことかを知っている。
当時は毎日のようにあって、くたくたになっていた時間が、いまは「宝物のような1時間」に変わった。
そして私はもう、役を間違えない。ちゃんと「空の国のことば」も覚えたし、「ピーマンまん」の扱い方も知っている。
彼女の目の中にある世界に、少しだけ入れるようになった気がする。
ごっこ遊びは、今でも続いている。
あの頃より短く、でもずっと深く。
大人には見えないけど、そこにある“世界”
「ごっこ遊びって、意味あるの?」
以前の私なら、そう思っていた。忙しい毎日の中で、時間も体力も削られる即興劇。
でも今なら、こう答えられる。
意味なんて考えなくていい。ただ、“そこにいること”が大事だったんだと。
娘のなかにある無限の世界。そこに入れてもらえることが、どれだけ貴重で、かけがえのないことだったか。
今はもう一緒に暮らしていないけれど、週に一度の“再会”で、彼女はまた「ごっこ遊び」で私をその世界に招いてくれる。
紙コップひとつで魔法が使える世界。
ティッシュのかけらが宝石になり、靴下がドレスになる世界。
大人には見えないけど、確かにそこにある“物語”を、私はこれからも大切にしたい。
ごっこ遊びは、ただの遊びじゃなかった。
娘が私に手渡してくれた、小さな小さなラブレターだったのだ。